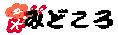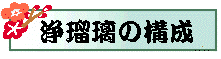
浄瑠璃の時代物は五段形式で
初段(序)事件の発端
二段(破の序)事件の展開
三段(破の破)事件の頂点
四段(破の急)事件の転換
五段(急)事件の解決
という構成をとっており、当然、三段目および、四段目が全体のヤマ場になります。 世話物の場合は、時代物にくらべて全体が短く、たいてい「上・下」、あるいは「上 ・中・下」といった二、三段にまとめられています。最初の作品といわれる『曽根崎 心中』の場合は一段で三場面という形ですが、実質は上・中・下と考えていいでしょ う。つまり、
上の巻=観音めぐり・生玉
中の巻=天満屋(てんまや)
下の巻=天神森(てんじんのもり/道行・心中)
という構成になっています。
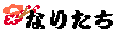
世話浄瑠璃の第一作として文楽史上にのこる作品です。実際に大阪にあった心中事件 を脚色したもので、事件から一ヵ月あとに上演されたといいます。 元禄十六(1703)年の竹本座で、作者はもちろん近松門左衛門です。江戸時代に は後世の改作が行われていましたが、昭和31年に新しく作曲して復活され、以降た びたび上演され海外でも好評を博しています。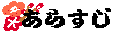
【生玉社前】
曽根崎の遊女天満屋のお初が田舎客と観音めぐりして生玉社へ着くと、そこへなじ みを重ねた仲である平野屋の手代徳兵衛が通りかかるので、お初は走りよってこのと ころ逢瀬のなかった愚痴を述べます。 徳兵衛は主人からの縁談をことわるための金を調達しましたが、友達の油屋九平次 がたっての頼みに一時貸しにしたのが返らず、主人への返済の期日を明日にひかえて 心を苦しめています。おりよく九平次が通りかかったので、金の督促をしますが、九 平次は証文に押した印形は先月に紛失したもので、はかったといいはって、人前で恥 ずかしめ、はては踏み蹴るの乱暴をして引きあげます。 お初は客に連れ戻され、徳兵衛は男泣きに泣いて、夕暮れの町をあてどもなく去っ ていきました。【天満屋】
その夜、なかまの女たちが徳兵衛の噂をするのに心を痛めていたお初は、忍んでき た徳兵衛をみつけ、うちかけの裾に入れて縁の下に隠します。 そこへ九平次があらわれて、またしても徳兵衛の悪口雑言を吐くので、お初が一人 言になぞらえて死ぬ覚悟を問うと、縁の下では徳兵衛がお初の足首を喉にあててそれ に答えます。やがて人々が寝静まると死装束に着がえたお初は徳兵衛と店を抜けだし ます。【天神森(道行】
死出の旅へといそぐお初、徳兵衛の二人は曽根崎の天神の森へたどりつきます。お 初は二人いっしょに死ぬうれしさのなかにもあとに残る父母のことを考えて涙にむせ ぶのでした。いつまでいっても果てのないこと、やがて女の帯で二人の体をくくりあ わせ、徳兵衛が抜いた脇差しを女ののどもとに刺しつける、と哀れをさそうように近 くの寺から朝の円向(えこう)の鐘と読経の声が聞こえてきました。
作としては「天満屋」が中心で、特に縁の下に隠れた徳兵衛に、お初が足先で死の 覚悟を伝えるとことは感能的な美しさがあります。「天神森」の「この世の名残、夜 も名残」以下の道行は近松の作品中でも代表名文として、国語の教科書にも使われて います。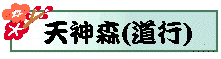
この世の名残り、夜も名残り。死に行く身をたとふれば
山田庄一『文楽入門』参照
あだしが原の道の霜。一足づつに消えて行く、夢の夢こ
そ哀れなれ。あれ数ふれば暁の、七つの時が六つ鳴りて
残る一つが今生の鐘の響の聞き納め。寂滅偽楽(じゃく
めついらく)と響くなり。鐘ばかりかは、草も木も空も
名残り見上ぐれば、雲心なき水の面北斗は冴えて影うつ
る星の妹背の天の河。梅田の橋を鵲(かささぎ)の橋と
契りていつまでも、われとそなたは女夫星。必ず添ふと
すがり寄り、二人がなかに降る涙、河の水嵩(みかさ)
も勝るべし。
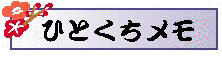
近松ごろの入場料には桟敷(さじき/左右、正面にある桝単位の席)と札銭(ふだせ ん/平土間にある個人単位の席)との二つに大きく分かれていた。亨保九(1724) 年武田芝居が奈良で興行したときの入場料が、桟敷一日九百文、札銭二十四文であっ たといいます。(今昔芝居鑑)
近松よりも時代は下がりますが、寛延三(1750)年に次のような入場料をあげています。歌舞伎芝居
上桟敷 一貫三百文。下桟敷 一貫五十文。詰込 五十文。札 二十文。
操り芝居
上桟敷 九百五十文。下桟敷 九百文。詰込 三十四文。札 二十文。
からくり芝居
桟 敷 二百文。札 十文。追加 五文。
これによって歌舞伎と操りとからくりの入場料を知ることができます。操り芝居の入 場料は歌舞伎にくらべて、だいたい七割くらいに当たり、桟敷が九百文余(約六千七 百五十円余)、札銭が二十文余(約百五十円余)であったことが知られます。 近松ごろの町人の財産は五百貫匁(約二億五千万円)以上を分限(ぶげん)、千貫以 上を長者と呼んでいました。近松の「冥途の飛脚/めいどのひきゃく」に出てくる飛 脚問屋の主人忠兵衛は二十貫匁(約千万円)にたらぬ財産でしたが、これら人たちが 歌舞伎・操り芝居を含めて一貫文(約七千五百円)前後の桟敷に行くことは易いこと でした。しかし、一日の手間賃が三匁(約千五百円)の井戸堀や、一日が二十文(約 百五十円)そこそこの女内職や、一年の給金二百匁(約十万円)のお針女などは三十 文前後の詰込、ないしは二十文前後の札に行くのがやっとのことだと思われます。 しかし、その詰込や札の人たちが芝居興行を支える大きな力となっていたようです というのも、元文二(1737)年江戸の中村座が南町奉行に差し出した売上高の控え をみると、桟敷代百十貫四百文(約八十二万八千円)、中下場、末の場等の代は計( 百六十貫九百十四文(約百二十万六千八百五十五円)であったといいます(高野辰之 博士『日本演劇史』参照) このように桟敷よりも、それ以外の売上高が全体の六割を占めていることに注目でき ます。すなわち桟敷の旦那衆よりも詰込や札の奉公人たちが芝居を支える大きな力と なっていることがわかります。どうも近松は、このような観客を考慮に入れながら、 奉公人の立場にたった世話物を作品に選んだと考えられます。 『近松門左衛門集』〔小学館〕参照